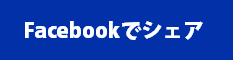現在の学生は、情報化社会の真っ只中で育ってきた世代です。あなたは、気軽に手に入れることができる情報を使いこなせているでしょうか?使いこなせているようで意外と使いこなせていないと思います。
今回は、テレビ・雑誌・新聞などのマスメディアについてこれからに役立つ見方を紹介します。

「情報社会の迷子」になっていないか
まず、皆さんには「情報社会の迷子」という言葉を紹介します。おそらくググっても出てきません。私が今作ったからです。この言葉の意味とは生まれた時から情報化社会で育った学生のあなたにとっては、「情報をどうやって得るのか」という問題より、「情報をどうやって選別するのか」ということの方が問題だったと思います。
現在では、就活で特に顕著に見ることができますが、その情報量に戸惑っている人が多く見受けられます。「情報社会の迷子」から脱皮する方法をこれから述べていきます。
情報の種類
情報は3種類に分類することができると言います。それは、「電波情報」「活字情報」「人的情報」です。「電波情報」ではテレビやラジオなどの情報、「活字情報」には新聞、雑誌、単行本、ネット上の情報、「人的情報」は直接人から聞く情報が挙げられます。
これらは、電波・活字・人の順番で入手する難易度が変わって来ることは経験として感じることができるでしょう。
情報は変わる?
新聞は各社によって立場が違う情報を提示していると言われています。1社だけの情報を信じているととても偏った考えが生まれてしまうかもしれません。新聞は活字情報に当てはまるものです。電波情報に当てはまるテレビのニュースでは、新聞が取り上げられることがあります。それによって、各新聞社の意見にテレビ局独自の意見をプラスして発信されます。
「伝言ゲーム」をやったことがある人はわかるかもしれませんが、事実は、人を介在する毎に変わってきてしまうものです。意見が2重になって発信されているということはそれだけ事実から離れていると言えます。それが、正確な情報だということができるでしょうか。
正確な「事実」に近づく方法
正確な事実に近づくためには、新聞やテレビでは「1社のみでなく数社見る」ということがまず挙げられます。すると、同じニュースに関しても違うことを言っているというようなことに気がつくでしょう。
さらに、少し手間がかかりますが「ソース(情報源)を見る」と いうこともおすすめします。各ニュースを発信している媒体では元々のソースを基に主張などを組み立てて発信をしています。その主張が入っていない状態の情報を見ることが事実に近づく方法であると言えるでしょう。
同様に、就活に関するネット上の噂などでもソースに近づく努力をすることにより、正確な事実にたどり着くことができる確率が大幅に向上すると言えるでしょう。
出てきた情報を鵜呑みにするのではなく、疑う癖が重要だと言えます。
ぜひ、正確な情報を身につける方法を実践して情報社会をうまくわたり歩こう!!
- 【28卒限定】企業の採用ブランド調査アンケート(26年春)に答えてAmazonギフト券をもらおう 2026/2/20
- 【SYNTH(シンス)ELK神戸旧居留地25番館ブログ】~周辺イベントのご案内~ | 株式会社SYNTH 2026/2/20
- 企業の採用ブランド調査アンケート(25春)に答えてAmazonギフト券をもらおう 2026/2/19
- 企業の採用ブランド調査アンケート(24秋)に答えてAmazonギフト券をもらおう 2026/2/19
- 【SYNTH(シンス)姫路ブログ】姫路駅から徒歩4分、すぐに“仕事モード”へ— 都市の利便性と、集中できる静けさを両立するワークプレイス — | 株式会社SYNTH 2026/2/18
- 28卒の就活はいつから?選考の解禁スケジュールや29卒・30卒の動き方まで解説 2026/2/13
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】~保護犬譲渡会イベントのご紹介~ | 株式会社SYNTH 2026/2/12
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】~グルメレポート第二弾 焼賣太樓(中華) ~ | 株式会社SYNTH 2026/2/9