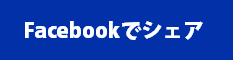インターンシップの重要度は年々高まり続けており、就活を有利に進めていくには、インターンシップの参加が必須となりつつあります。しかし、何社くらいのインターンにエントリーすれば良いか分からない方は多いでしょう。
本記事では、インターン応募の平均や目安・複数参加するメリットについてご紹介します。
インターンの応募締切はインターンシップガイドで確認しよう
インターンシップガイドでは、大手・人気企業のインターン締切が一覧になったカレンダーを好評配信中です。
エントリーに必要な提出書類もタグですぐに確認できるので、効率よく就活を進めたい方におすすめ!ぜひご活用ください
- ・学生はインターンに平均何社くらい応募している?
- ├応募の平均は約9社
- ├参加の平均は約6社
- └サマーインターンの平均は1〜4社
- ・インターンは何社くらい出すべき?エントリー数の目安をご紹介
- ├1dayのプログラムは8社以上出す
- ├2~4daysインターンは7社以上出す
- ├5days程度のインターンは3社以上出す
- ├長期インターンは2社以上出す
- ├サマーインターンは5社以上出す
- └最低2社参加を目標にする
- ・複数社のインターンに応募するメリット
- ├本選考参加のチャンスが増える
- ├企業・業界への理解が深まる
- ├競合他社を比較できる
- └自分に合った企業か確認できる
- ・複数社のインターンに応募するデメリット
- ├体力的・精神的に負担がかかる
- ├選考対策に時間を割けなくなる
- └振り返りをする余裕がなくなる
- ・インターンに何社エントリーするかを考える上での注意点
- ├インターン選考の倍率を考慮して申し込む
- ├インターンに参加する目的を明確にする
- ├いくつ申し込むかは目的に応じて決める
- └無理のないスケジュールを組む
- ・インターンの探し方
- ├インターンシップ専門のサービスを利用する
- ├企業のホームページをチェックしてみる
- └大学のキャリアセンターで相談してみる
- ・最後に
学生はインターンに平均何社くらい応募している?
ここでは、「マイナビ2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査」を元に、応募や参加の平均数をご紹介します。他の学生は平均何社くらい応募しているのでしょうか。
応募の平均は約9社
同調査では、全国の大学3年生・大学院1年生のうち93%が、12月までに平均8.5社のインターンシップ・仕事体験に応募しているという数値が出ています。
ほとんどの学生がインターンシップ・仕事体験に応募しているため、内定獲得のためにはインターンシップの参加が重要だという認識が高まっているのでしょう。
なお、インターンシップ・仕事体験に初めて参加した時期は、3年生の8月が31.9%で最も多くなっています。多くの学生は、夏休みにサマーインターンシップへ参加することで、就活のスタートダッシュを切っていることが分かります。
参加の平均は約6社
同調査によれば、2026年卒の学生が3年生の12月までに参加したインターンシップの平均は5.9社となっています。
では、インターンの開催期間別の参加平均は何社になっているのでしょうか。「キャリタス就活2026学生モニター調査結果」によると、期間別の内訳は以下の通りです。
| 1dayのプログラム | 8.3社 |
|---|---|
| 2〜4日間のインターン | 2.8社 |
| 5日間程度のインターン | 1.6社 |
| 2週間以上のインターン | 1.2社 |
オープンカンパニー等を含めた1dayプログラムの平均参加社数は8.3社、2~4日間インターンは2.8社、5日程度のインターンは1.6社、2週間以上のインターンは1.2社であることが示されています。
期間が長くなるほど参加平均が減少するのは、選考が厳しくなったり、スケジュールとの兼ね合いが取れなかったりするからでしょう。
サマーインターンの平均は1〜4社
夏の長期休暇の期間は、多くの大学生が就活のスタートダッシュを切る時期です。前述のマイナビの調査から、9月までに84.2%もの学生がインターンへの参加を経験していることが分かります。
夏季休暇の期間(6〜9月)に行われるインターンをサマーインターンと呼びますが、「マイナビ2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査~中間総括~」によると、その参加平均は1〜4社が47.9%であり、約半数を占めています。
多くの学生がサマーインターンを活用しており、業界研究・企業研究・自身の適性理解を目的に参加しているようです。
ただ、26年卒のサマーインターンの参加社数の平均は5.1社であり、25年卒と比べ0.9社減少しています。この原因としては、インターンシップの定義の改定により一部インターンシップとして認められなくなったプログラムがあることや、数より質を重視し早期選考につなげようとする学生が増加していることなどが考えられるでしょう。
インターンは何社くらい出すべき?エントリー数の目安をご紹介
企業によっては、インターンで書類選考や面接を行う場合があり、応募した企業全てのインターンに参加できるとは限りません。そのため、選考に落ちる可能性も考慮した上で応募する必要があります。では、インターンは何社くらい応募すればいいのでしょうか。
1dayのプログラムは8社以上出す
1dayのプログラムは、参加人数によっては抽選が行われることもありますが、多くの企業で選考を行わずに実施されています。1dayのプログラムは1日で完結するため、積極的に応募しておくのがおすすめです。
ここまでにご紹介したインターン参加社数平均を元に考えると、8社以上は出しておくといいでしょう。
ただ、1dayのプログラムには企業説明を中心としたオープン・カンパニーや、仕事体験を含むものなどさまざまな種類があるため、闇雲に申し込めば良いわけではありません。インターンに参加する目的によって、自分に合うものを選ぶことが大切です。
たとえば、すでに企業理解度が高いにも関わらず企業説明のみのプログラムを受けてもあまり意味がありません。むやみに応募するのではなく、自分の企業への理解度や志望度に合わせてプログラムを選びましょう。
1dayプログラムに参加する意味を理解しておこう
2~4daysインターンは7社以上出す
2~4daysのインターンでは選考を設けている企業が多いため、倍率や選考内容などを見て「何社応募するのか」の判断をする必要があります。
前述のマイナビの調査によると、インターンシップ・ワンデー仕事体験の選考で「1回以上は選考に落ちたことがある」と回答した学生の割合は56.1%と、2人に1人以上が落選を経験しているのが現状です。このデータから、選考で落ちる可能性を十分に考慮した上で応募する必要があると分かります。
さらに、前述のキャリタスの調査によると、2~4daysインターンの平均参加数は2.8社です。選考に落ちる確率を配慮して2倍の5社、さらに余裕を持って7社以上は応募しておくといいでしょう。
5days程度のインターンは3社以上出す
5days程度のインターンは実務に近い体験をするプログラムが多いため、選考も厳しい基準で行われます。本選考優遇があるケースも多いため、5days以下のインターンよりもさらに選考通過率が低いと思っておきましょう。
前述のキャリタスの調査によると、5days程度のインターンの平均参加数は1.6社になっています。この数字を鑑みると、3社以上は応募しておくのがおすすめです。
長期インターンは2社以上出す
2週間以上の長期インターンは、より社員に近い立場で実務を行うため、志望動機・スキル・勤務時間などさまざまな条件が合わないと選考を通過できません。短期インターンと比べて募集人数も少ないため、選考難易度は間違いなく高いといえます。
とはいっても、「キャリア形成」や「スキル習得」など、短期インターンとは異なる目的で長期インターンに参加する学生がほとんどでしょう。1つの企業でしっかりとコミットすれば十分であるため、学業との両立を考慮した上でも、複数の長期インターンに参加する必要はありません。
選考難易度を考慮して最低でも2社以上応募しておくと安心です。
長期インターンがどんなものか知っておこう
サマーインターンは5社以上出す
夏は就活を始めやすい時期であるため、サマーインターンは応募者数が多く倍率も高くなる傾向にあります。前述のマイナビの調査によると、サマーインターンの参加者数平均は1~4社が最多となっていることから、最低でも5社以上は受けておくといいでしょう。
ただ、サマーインターンの参加目的は人によって異なります。業界・仕事の理解を深めたい人は興味のない業界も含めて多めに応募し、本選考につなげたい人は志望度の高い企業に絞るなど、自分の状況に合わせた判断をしましょう。
最低2社参加を目標にする
インターンシップは、少なくとも2社には参加することを目標にしてみてください。大学やアルバイトが忙しくて時間に余裕がない場合は、半日や1dayのプログラムをメインに参加しましょう。
近年はオンラインで実施されるインターンも主流になってきているため、とにかく業界研究や企業研究を進めたいという場合には有効的に活用するのがおすすめです。
ただ、12月〜3月の冬・春季休暇に行われるウィンターインターンの時期には、本選考に向けて面接などの対策が重要となってきます。比較的時間に余裕のあるサマーインターンの段階で、ある程度場数を踏んでおくといいでしょう。
複数社のインターンに応募するメリット
ここまでご紹介したように、インターンは1社に絞らず、複数社のインターンに応募した方がいいといえます。ここでは、複数社のインターンに応募するメリットを見ていきましょう。
本選考参加のチャンスが増える
インターンシップに参加すると、本選考につながる優遇を受けられる場合があります。その内容は企業によって異なりますが、たとえばインターン中に評価の高い学生が早期選考に推薦されるケースや、本選考のESや一次面接が免除されるケースが一般的です。
もし現段階で本命の業界があるならば、その業界のインターンに複数社応募することは本選考のチャンスにつながります。興味のある企業・業界は、必ずインターンに応募する前に本選考への優遇があるか調べておきましょう。
企業・業界への理解が深まる
インターンを探している時点では、まだ志望業界や職種を絞り切れていない人もいるでしょう。まだ決め切れていない人はさまざまな業界・職種のインターンに参加して、企業や仕事の魅力を知るきっかけにしてみてください。
複数社のインターンに参加することで、新たに興味のある業界・職種を見つけられるかもしれません。。特にサマーインターンのような早い段階では、イメージで企業・業界を絞らずに、さまざまな業界のインターンに参加するといいでしょう。
競合他社を比較できる
同じ業界のインターンに複数社参加すると、その業界の競合他社を比較できます。同じ業界の企業であっても企業によって働き方や社風などが異なるため、インターンに参加することで違いを体感しておくのがおすすめです。
競合他社と比較したその企業ならではの特徴を捉えられていると、本選考で「なぜ他社ではなく弊社を志望したのか」と聞かれたときに答えやすくなります。
業界研究や企業研究は企業のホームページや就活の情報サイトなどでも行えますが、インターンでリアルに感じるのとでは大きく異なるものです。ぜひ積極的に複数社のインターンに参加して、理解を深めておきましょう。
自分に合った企業か確認できる
社風や社員の雰囲気はネットの情報や口コミでは分かりにくく、自分に合っているか判断が難しいものです。インターンに参加し実際に社内の雰囲気や働く環境を知れば、その企業が自分のイメージと合っているか確認できます。
間違ったイメージのまま就職してしまうと、「思っていたものと違う」というギャップから、せっかく就職できた会社を辞めたいと思うかもしれません。内定を獲得することだけでなく、実際にその企業で働くことを意識して就活に臨みましょう。
複数社のインターンに応募するデメリット
一方で、複数社のインターンに応募することが必ずしもいいとはいえません。複数社応募するデメリットについて見ていきましょう。
体力的・精神的に負担がかかる
インターンに応募することで経験を積むのは大切ですが、多くの数を申し込みすぎると体力的、精神的に負担がかかります。特にインターンの選考に慣れていない段階では、面接への緊張などから想像以上に負担が大きくなるかもしれません。
また、アルバイトや部活をしている学生は両立が難しくなる可能性もあります。体調を崩してインターンに参加できなくなっては意味がないので、無理のない数のインターンに応募しましょう。
選考対策に時間を割けなくなる
インターンの選考には、ESや面接など複数の選考フローが設けられるのが一般的です。加えて複数社のインターンに応募すると、企業研究や選考対策に割ける時間が短くなってしまうでしょう。
十分な選考対策ができないまま選考に臨むと、複数社応募していても選考を通過できる可能性が低くなります。インターンに応募する際は、選考対策にかかる時間も考慮した上で応募しましょう。
振り返りをする余裕がなくなる
複数社のインターンに応募したとしても、十分な振り返りをする時間がなければ自己成長につながりません。何度も同じ失敗を繰り返すことになってしまいます。
インターンは参加できればいいのではなく、インターンやその選考での経験を本選考につなげることが重要です。そのため、選考に落ちてしまった場合はその原因を考え、インターン参加後は反省点と良かった点を整理し次に生かすというように、一つ一つに対して振り返りをできる余裕をもって応募しましょう。
インターンに何社エントリーするかを考える上での注意点
インターンに何社参加するかを考える際には、以下の注意点を押さえましょう。
・インターン選考の倍率を考慮して申し込む
・インターンに参加する目的を明確にする
・いくつ申し込むかは目的に応じて決める
・無理のないスケジュールを組む
インターン選考の倍率を考慮して申し込む
インターンは誰でも参加できるわけではなく、選考を通過しなければならない場合があります。特に大手や有名企業のインターンは応募者の数が多く、倍率が100を超えることも少なくありません。
応募する企業を絞っていると、万が一全ての選考に落ちてしまった場合に、1つも参加できなくなってしまう可能性があります。仮に選考を通過したインターンシップの中で日程がかぶってもキャンセルや辞退はできるので、想定している参加数よりも多めに応募するといいでしょう。
インターン選考の倍率について理解しておこう
インターンに参加する目的を明確にする
インターン選びで失敗しないためには、まずインターンに参加する目的を明確にしておく必要があります。なぜなら、参加の目的によってインターンの選び方が変わってくるからです。
例えば、志望業界が決まっていない人には1dayのプログラムや5days以下のインターンがおすすめですが、志望業界が明確で就活のためにスキルを身につけておきたい人であれば長期インターンを選んだ方がいいでしょう。
インターン後のゴールをどのように見据えているのかによって、適したインターンは変わってきます。参加前に必ず目的を言語化しておきましょう。
インターンの参加目的を聞かれたらどう答える?
いくつ申し込むかは目的に応じて決める
一部では数十社以上のインターンに参加する人もいますが、数が多ければいいものでもありません。目的に合致したプログラムに参加し望む結果が得られれば、2〜3社で十分な場合もあるでしょう。
インターンに参加する際に大切なのは、参加した社数ではなく、目的に合ったインターンを選ぶことと意欲的な姿勢で参加することの2つです。ある程度の場数を経験しておくことも大切ですが、視野が狭くならないように注意しましょう。
無理のないスケジュールを組む
特に1dayのプログラムや短期インターンなどは、興味のある企業があれば可能な限り応募するのがおすすめです。より多くの業界・企業を知る機会が増え、就活で重要となる「情報」をそれだけ多く集められます。
しかし、インターンに注力しすぎるあまり、学業や他の就活対策などを蔑ろにするのは良くありません。
就活ではインターンに参加するだけでなく、筆記試験対策や面接の準備もする必要があります。複数社のインターンに応募するときは、無理のないスケジュールを組むようにしましょう。
インターンの探し方
何社のインターンに参加すべきかが理解できたところで、ここからはインターンの探し方をご紹介します。
インターンシップ専門のサービスを利用する
効率的にインターンを探すなら、インターンシップ専門のサービスを利用するのがおすすめです。業界や職種、勤務地など希望の条件で絞ってインターンシップを探せるので、素早く自分の希望に合ったインターンを見つけられます。
インターンシップ専門のサービスでは、登録者限定のイベントが行われることも多く、就活に必要な情報を総合的に収集できるのがメリットです。
インターンシップガイドでは、インターンを通年でご紹介しているだけでなく、インターン締切カレンダー・インターン体験記など、就活に役立つ情報をまとめています。ぜひこの機会に活用してみてください。
企業のホームページをチェックしてみる
志望する企業が決まっている場合は、その企業のホームページをチェックしてみましょう。多くの場合、「新卒採用ページ」や「リクルートページ」にインターンシップの募集情報が掲載されています。
また、ホームページに募集情報がなくてもインターンシップを実施していることがあるので、メールで直接企業に連絡して聞いてみるのもいいでしょう。ただ、その際は企業に失礼のないよう、必ずマナーを守って問い合わせてください。
大学のキャリアセンターで相談してみる
大学のキャリアセンターには、インターンシップ募集の情報が集まっています。就職課やキャリアセンターでインターンの募集について聞いてみましょう。
大学によっては、インターン参加が単位として認定されることもあります。単位認定されるには業種や期間など条件が指定されていることもあるので、大学の窓口で確認してみてください。
最後に
人によって参加するインターン数は異なりますが、参加の平均は6社、応募の平均は9社となっています。選考に落ちてしまうことや、さまざまな業界や企業の研究ができることを考慮すると、インターンは複数社エントリーした方がいいでしょう。
まずは選考のない1dayのプログラムや短期インターンにだけ参加するのもおすすめです。インターンシップガイドでは、さまざまな企業のインターンを通年でご紹介しています。インターンをお探しの学生の方は、ぜひご活用ください。
インターンシップガイド会員登録の特典
-
厳選インターン情報
短期、長期、学年不問などの全国のインターン募集情報を探せる!
-
締め切りカレンダー
人気インターン締め切りや就活イベントをカレンダーでチェック!
-
先輩の体験記
企業毎のインターン体験談や内定者のエントリーシートが読める!
-
企業からの特別招待
企業から交通費や選考免除等の嬉しい特典の招待が届くことも!
- 【SYNTH(シンス)姫路ブログ】姫路駅から徒歩4分、すぐに“仕事モード”へ— 都市の利便性と、集中できる静けさを両立するワークプレイス — | 株式会社SYNTH 2026/2/18
- 28卒の就活はいつから?選考の解禁スケジュールや29卒・30卒の動き方まで解説 2026/2/13
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】~保護犬譲渡会イベントのご紹介~ | 株式会社SYNTH 2026/2/12
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】~グルメレポート第二弾 焼賣太樓(中華) ~ | 株式会社SYNTH 2026/2/9
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】施設のご紹介 ~26年度 第3弾~ | 株式会社SYNTH 2026/2/5
- 【SYNTH(シンス)堂島ブログ】★中華そば・まぜそば びじねす食堂★ | 株式会社SYNTH 2026/2/3
- 仕事が早い人 | 株式会社SA 2026/2/2
- 数字とは | 株式会社SA 2026/2/2