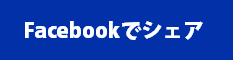水産学部を卒業した学生は、どういった就職先へ進むことが多いのでしょうか?まだまだ水産学部自体が珍しい学部のため、大学で学んだことをどのように活かせるかが気になる就活生も多いでしょう。
そこで今回は、水産学部の学生に人気の就職先や就職対策を解説していきます。ぜひ参考にしてください。

- ・水産学部では何を学ぶ?就職先は多い?
- ├水産学部の強み
- ├水産学部の就職難易度
- └大学院進学も選択肢
- ・水産学部の主な就職先
- ├食品メーカー
- ├農林水産省などの公共機関
- ├漁業・養殖業
- ├サービス・レジャー施設
- └その他水産関連の業界
- ・水産学部の就職に活かせる資格
- ├海技士・潜水士・小型船舶操縦士
- ├学芸員
- └教員免許
- ・水産学部の就活で注意すること
- ├自分のやりたいことができるかを確認する
- ├勤務時間をチェックする
- └幅広い業界を調べる
- ・水産学部の学生におすすめの就活対策
- ├資格を取得する
- ├大学院で専門分野の研究を深める
- └インターンに参加する
- ・最後に
水産学部では何を学ぶ?就職先は多い?
水産学部では、水産生物に関わるあらゆることを学びます。漁業・加工・流通などの様々な専門知識を身につけ、水産業界を支える人材を育成する学部です。水産に関連する仕事は豊富ですが、水産学部の就職先は多いといえるのでしょうか?このトピックでは、水産学部の就活事情についてご紹介します。
水産学部の強み
水産学部の強みは、ずばりその専攻自体にあります。実は「水産学について大学で本格的に学んでいる学生は珍しい」のです。
水産学は日本の水産資源を守ったり、消費者の生活を支えたりと様々な場面で応用できる重要な学問といえます。しかし、水産系の学部がある大学は2025年の現時点で、全国に約20校ほどしかありません。
こうした背景から、需要の大きさに対して専門知識を持った水産学部出身の学生が少ないというのが現状です。そのため、水産学を専攻していること自体が強みになるといっても過言ではないでしょう。
また、水産学部では医療や経営学といった幅広い観点から水産について学びます。その知識は多くの就職先で活かせるため、幅広い分野で働けるという強みに結びつくでしょう。
水産学部の就職難易度
水産関連のあらゆる専門知識を深めてきた水産学部出身の学生は、企業からの評価・需要ともに高く、就職難易度は比較的低いといえます。学問の応用が利くので、専門知識を活かせる就職先も多く、幅広い選択肢が取れるでしょう。
日本は海に囲まれており、古くから水産業が人々の生活を支えてきました。メーカーや造船業など、その最前線で活躍する人材のニーズは高く、就職率も高い傾向にあります。
水産学部では、多くの大学で独自のカリキュラムが組まれているのが特徴です。面接で「専門的に履修していた学問」について聞かれる場合があるため、志望企業や業界と関連を持たせたうえで回答できると良いでしょう。
大学院進学も選択肢
研究職や技術職といった専門性の高い職種を目指す場合は、大学院への進学も選択肢となります。最低でも修士レベルの知識を求める企業が多いので、あらかじめ大学院への進学を想定しておくのがおすすめです。
研究職や技術職では「企業の求める専門人材であるか」が重要なポイントとなります。自分の専門性の高さをアピールするためにも、大学院で研究を深め、卒論や面接などでしっかりと研究の成果を強調しましょう。
水産学部の主な就職先
ここからは、水産学部の学生の就職先として人気の業界を紹介していきます。自分に合う業界を探すのに是非お役立てください!
食品メーカー
食品メーカーでは水産物を扱う企業が多く存在します。大学で学ぶ内容と親和性が高いことから、水産学部の就職先として真っ先に思いつくという人も多いのではないでしょうか。
メーカーの中でも特にホワイト企業が多い傾向にあるため、福利厚生の観点からも人気の就職先です。
しかし、消費者と直接関わりのあるBtoC企業は知名度が高く、選考も厳しくなる傾向にあります。しかし、水産学部ならではの専門性をアピールできれば、比較的有利に就活を行えるでしょう。
農林水産省などの公共機関
水産学部では、民間就職以外にも公共機関への就職も選択肢となります。例えば水産庁や農林水産省といった、水産系研究・技術者などの募集が一般的です。
まだまだ世間的に認知度の低い水産学部ではありますが、水産学部卒業者を対象に募集がかかることが少なくありません。公共機関への就職や、研究職・技術者としての就職を狙う方は、情報が出ていないかこまめにチェックしておきましょう。
その他、大学教授や高校教員なども人気の就職先です。公共機関への就職には公務員試験への合格が必要です。スケジュール管理には気をつけ、可能な限り早めに動き出せるようにしましょう。
漁業・養殖業
漁業・養殖業は魚介類を捕獲・養殖する産業です。環境保全や資源保護といった資源を守る活動も総合的に行っています。水産学部で研究してきた「水産物の有効利用」に関する知識が活かせる、おすすめの業界です。
漁業・養殖業には、日常的に自然と関われるという魅力があります。島国の日本に深く根付いた魚食文化を支えられることも、大きなやりがいにつながるでしょう。
職種によっては小型船舶操縦士といった資格が必要となるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
サービス・レジャー施設
水族館などの水産に関連したサービス・レジャー施設も人気な就職先のひとつです。
海の生き物と触れ合うだけではなく、来場者に生物の特徴や魅力を伝えたり、希少生物の保護・調査などをしたりと、業務内容は多岐に渡ります。全年齢を対象としたサービスであること・学問としての役割を持つ仕事であることから、将来生の明るい仕事だといえるでしょう。
特に、水族館の飼育員は狭き門でありながら、大きなやりがいから非常に高い人気を持つ就職先です。潜水士や学芸員といった資格を持っていると就活で有利になる場合があるので、しっかりとチェックしておきましょう。
その他水産関連の業界
造船や海運業といった、その他の水産に関連した就職先も人気があります。学問の応用が利きやすいので、医薬品・化学工業・IT業界などでも水産学部での知識を活かせるでしょう。
水産学自体がオールマイティーな学問なので、一見関連性のない業界であっても大学で学んだことを活かせる場合が少なくありません。就職先に悩んでいる方は、まずはことから始めてみましょう。
水産学部の就職に活かせる資格
ここでは、水産学部の学生におすすめの資格を紹介します。資格の取得は、専門分野の強調や希望職種へのアピールに有効です。自身の就職活動に活かせそうな資格をぜひ探してみてください。
海技士・潜水士・小型船舶操縦士
将来、漁業に関わりたい学生は、海技士や小型船舶操縦士のような船員資格や、潜水士といった資格が就職に役立つでしょう。
海技士は一定の乗船経験が必要になるため、大学生は先に筆記試験だけを受けておくのが一般的です。卒業後、乗船経験を積んでから口述試験へと臨みます。
就職先によっては資格の取得が必須となる場合もあることに注意しましょう。特に船員資格は船舶の総トン数によって取るべき資格が変わるため、事前にどの資格が必要なのかチェックしておくのがおすすめです。
学芸員
学芸員とは博物館に勤務する専門職で、文化財や資料の収集・保管・展示・調査・研究・教育普及活動などを行います。特に、博物館や水族館といった就職先を目指す水産学部の学生におすすめです。
学芸員の資格は、大学で行われる学芸員養成の科目を履修していれば、卒業と同時に取得できるようになっています。その他、文部科学省の学芸員資格認定を受験することでも取得できるので、大学に授業がない場合はこちらをチェックしましょう。
教員免許
在学中に教員免許を取得し、卒業後に教師として働く学生も少なくありません。教員免許は、水産を学びたい後進の学生に教育を行いたい方におすすめの資格です。
教師として働くためには資格が必須となるほか、研修を受けなければならない場合があるので取得漏れがないよう注意が必要です。大学によっては資格取得に向けたカリキュラムが組まれているので確認してみましょう。
水産学部の就活で注意すること
幅広い就職先を選択肢に持てる水産学部だからこそ、就職活動時に進路に迷う学生も少なくありません。ここからは、就職先を選ぶポイントを紹介していきます。
自分のやりたいことができるかを確認する
水産学部は専門分野を幅広い仕事に活かせます。だからこそ、自分のやりたいことができる就職先であるかは必ずチェックしましょう。
例えば、水産資源学を活かした就職先に就きたいのであれば、水産業や水族館などがピッタリです。自身の専門分野に関連した就職先を選ぶと、就職後の自分をイメージしやすくなるほか、面接で専門知識や技術などの強みをアピールできるといったメリットがあります。
反対に、専門外で自分のやりたいことを実現したい場合には、志望動機を明確に示す必要があります。アドバンテージを失ってしまう分就職活動のハードルは上がってしまいますが、熱意を伝えられるように意識しましょう。
勤務時間をチェックする
特に漁業系の仕事は就職先によって勤務時間がバラバラなため、事前に確認することが大切です。早朝や深夜の勤務であったり、何日も連続で勤務する必要があったりと、事前確認が不十分だと希望する環境で働けない可能性があります。
将来的に多くの時間を船の上で勤務することが予想される場合、自分に合う環境を選べるように企業分析をしっかりと行いましょう。
幅広い業界を調べる
メーカー・水族館・漁業など、水産学部には非常に豊富な進路があります。そのため公共機関や大企業といった選択肢に囚われず、できるだけ視野を広く持っておくことが大切です。
自分の適性とかけ離れた就職先を選んでしまうと、早期退職につながる恐れがあります。企業分析や自己分析に時間をかけ、自分のやりたいことを客観的に考えることで、企業とのミスマッチを防ぎましょう。
少しでも気になる業界や企業があれば、まずはインターンに参加してみるのがおすすめです。インターンシップガイドでは1万社以上のインターン・企業情報を掲載しているので、ぜひご活用ください。
インターンシップガイド会員登録の特典
-
厳選インターン情報
短期、長期、学年不問などの全国のインターン募集情報を探せる!
-
締め切りカレンダー
人気インターン締め切りや就活イベントをカレンダーでチェック!
-
先輩の体験記
企業毎のインターン体験談や内定者のエントリーシートが読める!
-
企業からの特別招待
企業から交通費や選考免除等の嬉しい特典の招待が届くことも!
水産学部の学生におすすめの就活対策
志望する企業へ就職するためには、どのような対策が必要になるのでしょうか?ここでは、水産学部の学生におすすめの就活対策を解説します。
資格を取得する
就職先によっては、特定の資格を取得していないと応募できない場合があります。事前に応募要項や仕事内容をしっかりと研究しておくことが大切です。
必須ではなくとも、資格を持っていると希望職種へのアピールになったり、就職後に管理職を目指したりする場合などに役立ちます。会社によっては資格手当がつくこともあるため、志望する業界に関連した資格を一度チェックしてみるのがおすすめです。
大学院で専門分野の研究を深める
特に研究職・技術職を志望する場合には、いかに研究の成果を出せるかが大切となります。そのため、学外の活動などに力を入れるよりも、まずは自身の研究を深めていくことが大事であるといえるでしょう。
水産学部は学校での研究が仕事に直結しやすく、関連業界ではその専門性が評価されています。大学院への進学や推薦就職などを考慮しても、学内での活動に力を入れるのがおすすめです。
インターンに参加する
インターンへの参加は、水産学部の学生にも非常におすすめの就職対策です。インターンに行く目的は大きく分けて2つあります。
インターンに参加した経験が武器になる
インターンでは、先輩社員の側で実際の業務を学べます。業界に対する理解が深まり、志望動機も説得力のあるものが作成できるでしょう。人気の食品業界などはどこも倍率が高いため、周りの学生と差をつけられる点からおすすめです。
企業とのミスマッチを防げる
企業で実際に働いてみることで、自分の適性に合った就職先なのかがより正確に判断できます。就職してから後悔しないためにも、前もってインターンに参加しておくのがおすすめです。
幅広い選択肢を取れるからこそ、自分のやりたい仕事ができるのかをインターンを通して確認しておきましょう。
最後に
今回は、水産学部の就職先やおすすめの就活対策などをご紹介しました。水産に関連した就職先は幅広いため、水産学部の学生は自身の専門を活かして就職活動を比較的有利に進められます。企業とのミスマッチを起こさないためにも、インターンなどに参加して、事前に企業研究や自己分析を進めておくのが良いでしょう。
インターンシップガイドでは、1万社を超えるインターン・企業情報を掲載しています。その他、内定者のESや体験談などの就活に役立つコンテンツも配信しているので、ぜひお役立てください。
インターンシップガイド会員登録の特典
-
厳選インターン情報
短期、長期、学年不問などの全国のインターン募集情報を探せる!
-
締め切りカレンダー
人気インターン締め切りや就活イベントをカレンダーでチェック!
-
先輩の体験記
企業毎のインターン体験談や内定者のエントリーシートが読める!
-
企業からの特別招待
企業から交通費や選考免除等の嬉しい特典の招待が届くことも!
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】~グルメレポート第二弾 焼賣太樓(中華) ~ | 株式会社SYNTH 2026/2/9
- 【SYNTH(シンス)西梅田ブリーゼタワーブログ】施設のご紹介 ~26年度 第3弾~ | 株式会社SYNTH 2026/2/5
- 【SYNTH(シンス)堂島ブログ】★中華そば・まぜそば びじねす食堂★ | 株式会社SYNTH 2026/2/3
- 仕事が早い人 | 株式会社SA 2026/2/2
- 数字とは | 株式会社SA 2026/2/2
- ビジネスモデル | 株式会社SA 2026/2/2
- 【SYNTH(シンス)ELK神戸ブログ】~旧居留地内イベント情報 第31回神戸ルミナリエ~ | 株式会社SYNTH 2026/1/27
- 【SYNTH(シンス)ELK神戸旧居留地25番館ブログ】~施設紹介Vol.1~ | 株式会社SYNTH 2026/1/23